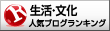イシモチって聞いたことありますか?
私は初めて聞いた時、お恥ずかしながら「固い餠?」と思った人間であります。
イシモチ(またの名をシログチ、ニベ
など)とは、石でも餅でもないお魚の名前。
釣り人の方の中ではポピュラーな魚なんだそうです。
スーパーなどで頻繁に出回る魚ではありません。
しかし、釣りに興味のない方でも、イシモチをお店で偶然手に入れた、釣り人にもらったという人もいるかもしれません。
実はお手頃なイシモチ、美味しい食べ方を調べてみましょう!
Table of Contents
イシモチは地域によって違う魚?!

イシモチはスズキ目ニベ科に属する海水魚で、主にシログチ(別称グチ)という魚をさし、地方によってはニベ、テンジクダイなどの魚を呼ぶ場合もあります。
シログチの体長は40cm程度で、体の色は銀白色です。
ニベの場合は体長50cm程度で個体によってはもっと大きいものも。
ニベの体には全体的に黒い斑点があり、シログチに比べると黒っぽく見えます。
地域によってイシモチ=シログチ・ニベだったり、ニベ=シログチだったり…
呼び方の区分は複雑なようです。
その複雑さは、「イシモチ」という名前の由来にも関係がありそうです。
イシモチは石を持つ魚?その名前の由来とは…

なぜ「イシモチ」、つまり石を持つと言われるのでしょう?
由来は、頭骨に大きな石のような骨があることにあります。
イシモチは、体の平衡感覚を保つための「耳石」が通常の魚より大きく、小石のような耳石を持っています。
これはニベ科の魚の特徴で、シログチと同じニベ科のニベも同様であるためか、関東ではニベもシログチも「イシモチ」の名で呼ばれているようです。
また、ニベ科ではない魚ですが、テンジクダイも耳石が大きいためイシモチの名で呼ぶ地域があるようです。
また、「シログチ」という名前にもユニークな由来があります。
シログチは釣り上げられると、浮き袋を振動させ「グーグー」という音を鳴らします。
それが愚痴を言っているように聞こえるということから、「グチ」「シログチ」と名がついたそうです。
イシモチを手に入れたら…美味しい調理法!

イシモチは高級かまぼこの材料としても重用されているんだとか。
でも、家庭で食べるときの調理法はどうすればいいのでしょう?
まずイシモチの特徴ですが、身は柔らかくて油が少なく、あっさりとしています。
鮮度が落ちるのが早い魚なので、早めに締めて血抜きし、内臓を取りましょう!
釣ってすぐ締めたような鮮度の良いものは、身に透明感があり、お刺身でいただくと絶品です!
しかし、スーパーなどで丸魚の状態で売られているものは血抜きされていなものが多いようです。
匂いが生臭い、身に透明感がないものは加熱調理するのが良いでしょう。
一番お手軽なのは、「塩焼き」です!
塩は好みで加減し、グリルやフライパンで焼いていただきましょう。
あっさりとした白身の魚なので、「ムニエル」や「唐揚げ」、「煮魚」などの調理法も人気です。
小さめのイシモチなら、唐揚げやフライにするを私はお勧めします。
イシモチは小骨が多い魚なので、油で揚げたら骨ごと食べやすいです。
甘酢あんをかけて南蛮風にするのも人気みたいですよ。
気になる保存法。鮮度に要注意!
上でも触れましたが、イシモチは鮮度がすぐ落ちてしまいます。
すぐに締める・血抜きすることが重要です。
また、鱗を落としてよく水洗いするのも、臭みを落とすコツです。
ちゃんと下処理もしたとしても、冷蔵庫や氷水で当日中~1日程度の保存が限度でしょう。
食べきれない場合はすぐに冷凍保存しましょう。
冷凍保存する場合も、しっかりと下処理をしましょう。
頭ごと使う予定がないなら、3枚に下ろしておいて、解凍後は加熱調理するのがおすすめです。
イシモチを食べてみたい!旬の時期はいつ?
 イシモチはほぼ一年中釣れる魚として釣り人たちには知られているようです。
イシモチはほぼ一年中釣れる魚として釣り人たちには知られているようです。
美味しい旬の時期についてですが、「秋~冬」派と「夏」派で意見が分かれています。
秋から冬にかけては、イシモチの身に脂がのり、お刺身が美味しいと言われています。
一方夏は、イシモチは産卵期を迎えるため卵を持っており、産卵のため沿岸での漁獲が増えるのだそうです。
あまり一般の市場に出回る魚ではありませんので、見つけたらラッキー!
水揚げの多い地域の魚屋さんなどでは手に入るかもしれませんね。
アジなどと一緒によく釣れるそうなので、釣り好きの方に頼んだり、いっそ自分で釣りに行くのもいいかもしれません。
夏も冬も、どちらもぜひ、一度味わってみたいですね!
まとめ
・イシモチは主にシログチのこと。地域によってニベ、テンジクダイなどをさす
・「イシモチ」の由来は、頭に石のような耳石を持つことから来ている。
・イシモチは鮮度が命。加熱調理がおすすめ。すぐに締め新鮮なら刺身も
・保存の際は素早く下処理。食べきれないなら冷凍保存を。
・旬は2通り。脂の多い秋冬と、産卵期の夏