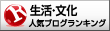誰しもやって来る年男年女。
よく耳にする言葉ですがただ自分が生まれた干支の年みたいな簡単な理解の方がほとんどでしょう。
よく聞く「年男年女」とはなんでしょう?
またその年に何かをしないといけないみたいなのはあるのでしょうか?
近い言葉で「厄年」があるけどこれは悪いこと意味なの?
疑問が多いと思うので1つずつ見て行きましょう。
Table of Contents
年男年女の意味
年男年女とは生まれた十二支の年を迎える人のことを指します。
ちなみに数え方は満年齢になるとき。 生まれた年を0年とし、12の倍数でくる年齢が年男年女に値します。
そして、年男年女の場合、多くの地域では縁起のいいものと考えられているようです。
年神様という毎年お正月にやってくる豊作や幸せをもたらす神様のご加護を年男年女の人たちは受けることができるとしており、縁起がいいと言われています。
また重要な神事や儀式に関わることもあり、
門松を立てるのが年男。豆まきは年男年女と決めている地域もあるようです。
このように日本では年男年女が神事や宗教の風習上、とても重要な役割を担っていると言えます。
しかし、消して縁起が悪いものではなく、むしろいいものだということですね。
年女・年男になる年にしておくこと
上記にも述べたように年男年女は地域によってはその年の神事にまつわることを任されることがあるようです。
その理由としては、神様が喜ぶことをすることでいつもより恩恵が受けれるチャンスがあるから。
ではしたことがいいことには何があるのでしょうか。
・年の暮れの大掃除
・お正月の飾り付け
・初詣
・若水(元旦の朝の初めての水)を汲む
・節分の豆まき
・恵方巻き
すべて仏教・日本ならではの神事まつわることですね。当たり前にやっていることもおおいですが、近年正月の飾り付けや節分をする家庭も減ってきているようです。年男年女の方は率先的に行って神様からの恩恵をいただきましょう。年は始めの願掛けとしての行いとしてもいいかもしれませんね。
厄年の意味
では年齢にまつわる言葉といてよく混同されがちなのが「厄年」。こちらの言葉を聞いただけであまり縁起のいいものではないことが分かる方も多いのではないでしょうか。
「厄年」:わざわいにあいやすく、忌み慎むべきものとされる年齢。
こちらの年齢は生まれた年を1歳として考える「数え歳」で考えます。また男性と女性で迎える歳が違うもの特徴。科学的な根拠は不確かではあります。しかし平安時代から根付いている風習のため、これを重んじる日本人はとても多いです。
・男性の厄年:25歳、42歳、61歳
・女性の厄年:19歳、33歳、37歳
そして男性の42歳、女性の33歳は大厄と呼ばれ、凶事や災難に遭う率が非常に高いとされているので、十分な警戒が必要なのです。
厄年にしておくべきこと

誰しも凶事や災難には遭いたくないもの。どうしたら回避することができるのでしょうか。
まず厄年を迎える歳にすべきではないこととして、人生の転機となるような結婚、出産、家を建てる、引っ越し、転職などは避けましょう。
とはいえどうしてもこういった人生の転機を厄年に迎えなければならないこともあるでしょう。
厄年を上手に乗り切る最大の方法、実は「気にしないこと」。
昔からの言い伝えだからこそ、その年齢になったときに何かしら不幸なことがあったときに「厄年だからだ・・・。」と思うかもしれません。
しかし、それ以外の歳に似たようなことが起こったとき、きっと原因を探るはずです。
人生における波は実年齢に関係な起こっていることがほとんど。
厄年だからといって気にしすぎないことが一番の対処法なのです。
でもできれば不幸は起きてほしくないし、厄年でも少し安心した状態で迎えたいですよね。
厄年を迎える方が一番している対策は「厄祓い」でしょう。
元日から節分前にするのが良いようです。また合わせて初詣の段階で厄除けのお守りを買っておきましょう。
これをしておくだけでも心持ちが随分と変わりますよ。
まとめ
・年男年女は生まれた十二支の年を迎える人のこと。
・年男年女は神様の恩恵を受けやすいとされており、縁起が良いとされている。
・年始の飾り付けや豆まきなどの行事を行うことでさらに恩恵を受けやすくなるとされている。
・厄年は災いが起こりやすいとされている年齢。
・気にしないことが一番の厄年対処法。
・厄祓いやお守りで自分の気の持ちようを変えるのも手。
年男年女と厄年は意味合いが全然違いますね。両方の運気を上げるにはやはりお参りなど神様にきちんと感謝することでしょう。
どちらも科学的根拠のないものですが日本に根強く残っている風習。
気にしないとは言え、神様への敬意は忘れないようにしましょう。